
「7つの習慣」って、有名だけど、なんか胡散くさい感じがするんだよなぁー。。
確かに、クセのあるビジネス書だと思うから認定コーチのワタシが有用性と違和感のポイントを伝えるね。
「7つの習慣」は世界中でベストセラーになる超有名な名著です。
ただ、その一方で
「何か怪しいし、胡散臭い…。。」
と感じてアクションにつなげられない人も多いと思います。
事実、ワタシも読み始める前は、そんな印象を持っていました。。
ただ、10年以上実践し、研修にも参加して資格を取得したことで何がポイントでどこが胡散臭いポイントかも分かりました。
そこで!今回は今までの経験で分かった、7つの習慣の有用性とビミョーなことの両方をお伝え致します!(‘ω’)ノ
ビビっときたTipsや手帳術を発信します ٩( ᐛ )و
●資格:国家資格キャリアコンサルタント
●実績:手帳歴18年 | 自作歴10年| デジプラ歴2年
●属性:30代2児の父 | 7つの習慣の資格も保有
目次
7つの習慣とは何か
「7つの習慣」のポイントを先にお伝えします。
「7つの習慣」は端的に言えば「成功哲学のまとめ本」であり、成功の原理原則がまとまっています。
もともと、原題は「The 7 Habits of Highly Effective People」というものです。
内容は、成功している人に関する書籍や研究を過去200年に遡って特徴をまとめた「まとめ本」です。
つまり、新しい独自のメソッドが述べられているのではなく、あくまで「数ある成功法則を体系化したもの」です。
そのため、極端のことを言えば、成功哲学系の内容が美しくまとまっているのでこれ1冊をマスターすれば他の本を読む必要はないです。
本のサマリーや、初めて読む時に押さえるイントなどは別の記事(読み始める前に押さえるべきポイント)でまとめています!

いきなり全部理解できなくても実践できるところから少しずつ理解していきましょう!
7つの習慣のそれぞれの実践ポイント
続いて「各習慣の実践ポイント」についてです。
各習慣の実践ポイントを端的に言うと下記の通りです。
さらに深掘りして、各習慣で下記の内容をまとめています!
- どんな内容か
- 実践するポイントは何か
- 全体的な特徴はどうか
ざっくりどんな内容かを理解するために使ってみてください٩( ᐛ )و
第1の習慣|主体的な行動の仕組みを作る

第1の習慣は端的に言うと「”主体的な行動”を増やす習慣創り」がメインテーマです。
一番のポイントは、周りの刺激にすぐに反応せずに一歩立ち止まって、行動を選択する習慣を作ることです。
- 反応的な行動を脱却する
- 価値観を見える化する
- インサイドアウトの回路を作る
他の全ての習慣の根本にあたる一番大事な習慣になりますのでぜひ定義と合わせて実践ポイントを押さえてみてください!
本書を読んで具体的なアクションプランに悩んだらまずは上記3点をどう実践するかを考えてみましょう!
- 実践ハードル ★★★★☆
- 得られる効果 ★★★★☆
- 連動・拡張性 ★★★★★
第2の習慣|ミッションステートメントの理解

第2の習慣は端的に言うと『正しい目標設定』がメインテーマです。
目的のあり方、目標設計の考え方・実践の仕方についてまとめられています。
- “2度作る”を実践する
- ミッションステートメントを作る
- ミッションを年表でまとめる
特にミッションステートメントの作成は7つの習慣の中核の一つで独特なアプローチです。
この章を読んで具体的なアクションプランに悩んだらまずは下記3点をどう実践するかを考えてみましょう!
- 実践ハードル ★★☆☆☆
- 得られる効果 ★★★☆☆
- 連動・拡張性 ★★★☆☆
第3の習慣|正しいタイムマネジメント方法

第3の習慣は端的に言うと『タイムマネジメント』がメインテーマです。
ただ、7つの習慣におけるタイムマネジメントというのは単純に時間を効率化するだけでなく
自分の価値観・ミッションを踏まえた上での時間管理の合理化することがポイントです。
- 緊急性と重要性のマトリクスを使う
- 前倒しの回路を作る
- リフレクションとデレゲーション
この章を読んで具体的なアクションプランに悩んだらまずは上記3点をどう実践するかを考えてみましょう!
誤解がされやすい領域ですが、非常に実践的な習慣なのでぜひ正しい理解と共に実践ポイントを押さえてください٩( ᐛ )و
- 実践ハードル ★☆☆☆☆
- 得られる効果 ★★★★★
- 連動・拡張性 ★☆☆☆☆
第4の習慣|Win-Winの作り方を知る

第4の習慣は端的に言うと『対人関係の分析視点』がメインテーマです。
対人関係を良好にするための考え方にフォーカスしているところがポイントです。
- 6つのパラダイムで分析する
- No Dealの選択肢を持つ
- Win-Winの実行協定を作る
この章を読んで具体的なアクションプランに悩んだらまずは上記3点をどう実践するかを考えてみましょう!
この後の第5・第6の習慣のベースになる考え方になるため、読み飛ばさずに、ここの理解をした上で読み進めていきましょう٩( ᐛ )و
- 実践ハードル ★★★★☆
- 得られる効果 ★★☆☆☆
- 連動・拡張性 ★★★★☆
第5の習慣|共感による傾聴を実践する

第5の習慣は端的に言うと『傾聴の押さえドコ』がメインテーマです。
7つの習慣の中では最も行動のイメージがしやすい内容で応用の範囲が広いです。
- 自叙伝的な反応を止める
- 共感による傾聴のステップを理解する
- ストロークの実施をする
この章を読んで具体的なアクションプランに悩んだらまずは上記3点をどう実践するかを考えてみましょう!
- 実践ハードル ★★★☆☆
- 得られる効果 ★★★★★
- 連動・拡張性 ★★★☆☆
第6の習慣|シナジーを創る土壌を作る

第6の習慣は端的に言うと『相乗効果の創り方』がメインテーマです。
この習慣ではシナジーという言葉が多く登場しますが言い換えるならば相乗効果です。
- ”シナジーの発揮”を理解する
- 1+1≠2のゴールイメージを持つ
- シナジーができるルールを作る
この章を読んで具体的なアクションプランに悩んだらまずは上記3点をどう実践するかを考えてみましょう!
- 実践ハードル ★★★★★
- 得られる効果 ★★★★★
- 連動・拡張性 ★☆☆☆☆
第7の習慣|効果的な1週間の計画を作る
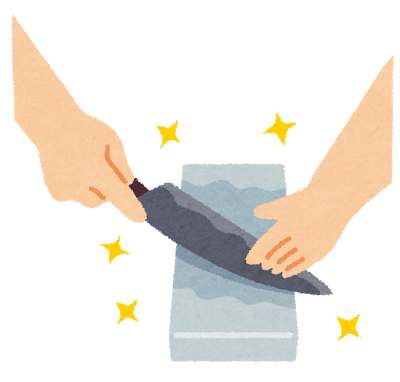
第7の習慣は端的に言うと『成長する仕組』がメインテーマです。
7番目に紹介されるものですが、この習慣は少し特殊で他の習慣とは独立しています。
そのため、第1〜6の習慣をした後にするのではなく、第1の習慣を実践する時から断続的に実践するべき内容です。
- 刃を研ぐの考え方を理解する
- 刃を研ぐ具体例40選
- 1週間コンパスで仕組化する
この章を読んで具体的なアクションプランに悩んだらまずは上記3点をどう実践するかを考えてみましょう!
各習慣の実践をしつつも並行して実践することで効果を高められるので、最も実行に移しやすいです٩( ᐛ )و
- 実践ハードル ★☆☆☆☆
- 得られる効果 ★★★☆☆
- 連動・拡張性 ★★★★★
7つの習慣が”気持ち悪い!”と言われるワケ

では次に「気持ち悪いと感じる理由」についてです。
これだけ有名な本なのに、なぜ
「気持ち悪い!」
と言われることが多いのでしょうか。
これには大きくは下記のようなマイナス面があるからだと考えられます。
順に触れていきます。
自己啓発・スピ系のジャンルだから
1つ目は「本のジャンル」です。
そもそも、自己啓発やスピ(スピリチュアル)系の内容は一定数の人から敬遠されています。
事実、ワタシの友人の中にも
「自己啓発系の本が好きな人は信用できない」
という人が一定います。
一方で、自己啓発やスピ系のジャンルが好きな人は、7つの習慣の内容は好みのジャンルです。
そのため、7つの習慣の内容うんぬんではなく、
「そもそも、このジャンルが気持ち悪い」
という理由で疎まれるケースが多いです。

ワタシもこのジャンルはちょっと…って感じだなぁ。
勧誘などにも使われるから
2つ目は「本の使われ方」です。
有名な自己啓発本は、多くの場合、怪しいネットワークビジネスの勧誘の時に使われたりします。
実際に、新宿のカフェでネットワークビジネスの勧誘を見かけたことがありますが、非常に見苦しいものでした。
そのため、似た体験をしたことがある人は、嫌悪の対象になるのも理解はできます。
自己啓発系は、効果が高く、人の解釈によってどうにでもとれるので悪用しやすい傾向があります。
そのため、この点も、怪しさポイントをあげてしまっている点は否めません。。

本来の価値を知っているだけに正しい使われ方をしないのは悲しいです。。
成功の定義が曖昧だから
3つ目は「成功の定義」です。
7つの習慣は、成功するための7つの原理原則などと解釈されることがありますが
原題は「The 7 Habits of Highly Effective People」であり
ビジネス上でうまく言っている人たちの特徴をまとめたものです。
そのため、”成功”と一口でいうとかなり曖昧で怪しい感じがしますが
「ビジネスマンとして成功している人の特徴」
として傾向分析の本として捉えると解釈がしやすいです。

成功っていっちゃうと人それぞれ解釈が違うもんね
理想的でハードル高いから
4つ目は「ハードルの高さ」です。
7つの習慣は、内容は理解しやすく、読んでいるうちは
「なるほど、なるほど…!」
となるものの、いざ実践!となると思うようにできず
「なんだよ、全然実用的じゃないじゃん」
と思う人も一定数います。
ただ、これは正しい理解と実践のコツを掴めていないケースがほとんどなので
応用のさせ方次第です。

今だにうまくできていないなぁと感じることが多々あります。。
過度なポジティブ思考に映るから
5つ目は「内容の捉え方」です。
7つの習慣は第1の習慣の「主体的に生きる」、「率先力を磨く」という考えがコアの思想です。
「どんなことでも、すべての原因は自分にあるとまずは考える」
という考え方が人によっては
「過度な自責思考で怖い。。」
「なんかパワハラを強要しているみたい。。」
とネガティブに捉えられてしまうことがあります。

怖いとも思うけど、事実、すごい人たちはできていることだからねぇ。。
7つの習慣が”名著だ!”と評価されるワケ

一方で「名著と言われる理由」は何か。
一部の人がネガティブに捉える反面、世界中の多くの人には受け入れらてビジネス書の名著の地位を築いています。
それはどうしてなのか。
大きくは下記の点がポイントだと考えられます。
順に触れていきます。
根拠に基づいた原理・原則だから
1点目が「根拠に基づく内容」という点です。
前述の概要でも述べたた通り、この本は成功哲学本のまとめ本です。
200年にものぼる内容をマルっと調査して独自に再構築した本のため、根拠に基づいた内容です。
著者1人の考えや経験だけで書いた本ではないため、信憑性が高く、本書で言われる原理原則も汎用性が高い内容になっています。
そのため、多くの自己啓発書を読み漁るくらいなら、これ1冊を深く読み込む方が圧倒的に効率がよいです。

7つの習慣がまとめ本だという認識はなかったなぁ…!
仕事から家庭まで応用の幅が広いから
2点目が「応用できる範囲」です。
7つの習慣の内容はビジネス上のことだけではなく、家庭でも応用がきく内容となっています。
事実、7つの習慣の中には多くの家庭内での実践例が示されており、
特に夫婦間の関係や親と子供の関係を改善する事例は数多くあります。
そのため、ビジネスマンだけが読むものではなく、万人が読むべき内容となっています。
実際、著者のスティーブン・R・コヴィー氏は9人の子供(!)と36人の孫(!!)がおり
この考え方を大切にして家庭にも応用し、家庭向け7つの習慣の本も出しています。
個人と社会の両立を包括した内容
3点目が「包括的な内容」です。
7つの習慣は、個人的な成長(私的成功)と社会的な成功(公的成功)の両面でポイントが整理されています。
他のビジネス書では「個人的な成長 or 社会的な成功」とどちらか一方を説明しているのが大半の中
7つの習慣は包括的に両面をうまく組みこんでいる点が独特であり、唯一無二の内容になっています。

7つの習慣がまとめ本だという認識はなかったなぁ…!
長期的な人生設計に役立つから
4点目が「長期視点の内容」です。
7つの習慣は長期視点で自分のことを見つめることができるため長期的な人生設計にも応用が利きます。
具体的には第2の習慣の中で、自己リーダーシップを発揮するという内容があります。
この自己リーダーシップを定義するためには、自分の価値観やミッションを考える必要があり
そのために、どのように成長してどのような状態で死にたいかと、人生を俯瞰する長期視点での考え方が提案されています。
そのため、この内容を自分に落としこむことができれば、自分の人生設計に役立ちます!
リーダーシップやイノベーションの洞察
5点目が「リーダーシップとイノベーション」です。
リーダーシップは4点目で述べた通りですが、7つの習慣ではイノベーションに類似した考え方がまとめられています。
イノベーションという言葉こそ使われていませんが、第6の習慣で述べられるシナジーとはいわゆるイノベーションの起こし方とも捉えられます。
そのため、社会的な成功を収めるために、どのようにして個人の力だけでなく周りの力も引き出せるかという点まで言及されています。
この点が多くの経営者にも支持される内容であり、本書の内容は日本の伝説的な起業家の稲盛氏とも共通する考えが多いようです。
7つの習慣を実践するアイデア3選
最後に7つの習慣の「実践アイデア」です。
7つの習慣の難しさの一つは
「やってみると想像以上に実践がむずい…」
と感じる点です。
そのため、ワタシが今まで実践してきた内容から厳選して、これは使いやすいと思うアイデアを3点紹介します。

実践するコツを掴めると、日々の充実度がグンと上がりますよ!
①仕事や家庭など身近な人にアウトプット
1点目が「身近な場所でアウトプット」です。
7つの習慣は応用の範囲が広いため、仕事だけではなく、家庭でも応用が利きます。
そのため、仕事上での同僚や、家庭内での親や子供やパートナーなど
身近な人にアウトプットをしていきましょう!
特に第4の習慣・第5の習慣は対人に向けた習慣であるため、共感的な傾聴など
とても実践的でアウトプットしやすい内容が多くあります。
②セルフコーチングの習慣を作る
2点目が「セルフコーチングの実践」です。
7つの習慣のポイントを日々実践する実践法として7つの習慣セルフコーチングというものもあります。
これは、自分の中に、小さな架空上のコーチを作り、自分で自分をコーチングする考え方です。
やり方さえおさえれば、いつでもどこでも使える考え方なので
第1の習慣・第2の習慣・第3の習慣の内容を踏まえて、セルフコーチングの考え方も会得しちゃいましょう!
③手帳を使ってルーティーン化
3点目が「手帳での応用」です。
7つの習慣のノウハウは手帳を使ってアウトプットすることで、本領を発揮します。
ちなみに、実は7つの習慣に準拠した手帳としてはフランクリン・プランナーというものがあるのでこれを使うのもオススメ。
ちなみに、フランクリン・プランナー以外の手帳でアウトプットしたいと言う人は、下記の本を使うと7つの習慣のアウトプットがしやすいです。

7つの習慣は分かりそうで分からないコトが多かった気がするなぁ。。
まとめ

以上、7つの習慣の原理原則と実践する際のポイントでした。
これらのアクションを自分の中で腹落ちさせて、日々の習慣にするまでには想像以上に時間がかかりますが、
これができると、7つの習慣を知らなかった時と比べて、信じられないほど、人生の充実度が変わります。
そして、これらは特に必要なスキルや特殊な知識はいらず、どの時代、どの職種、どのような年代な人でも等しく実践ができます。
誰でもできることだからこそ、日々の生活にいち早く組み込み、理想の人生を手にいれていきましょう!٩( ᐛ )و
ご精読頂きありがとうございました。
m(_ _)m









































→主体的な行動の仕組みを作る
→ミッションステートメントを理解する
→正しいタイムマネジメントを行う
→Win-Winの作り方を知る
→共感による傾聴を実践する
→シナジーを創る土壌を作る
→効果的な1週間の計画を作る